
「相続時精算課税制度」って耳にしたことがあるけれど、具体的にどんな制度か分からないと感じていませんか?
制度を利用することでお得になる一方、誤った理解や準備不足によって、後々大きな問題になることもあります。
この記事では、相続時精算課税制度の内容や、そのメリットとデメリット、注意点について詳しく解説します。
相続に関する準備を怠ると、家族にとって負担となり、円滑な手続きが難しくなることがあります。
しかし、適切な知識を持ち、事前に対応することで、相続手続きをスムーズに進め、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
ぜひこの記事を、相続手続きの準備や対策のヒントとしてお役立てください。
相続時精算課税制度とは
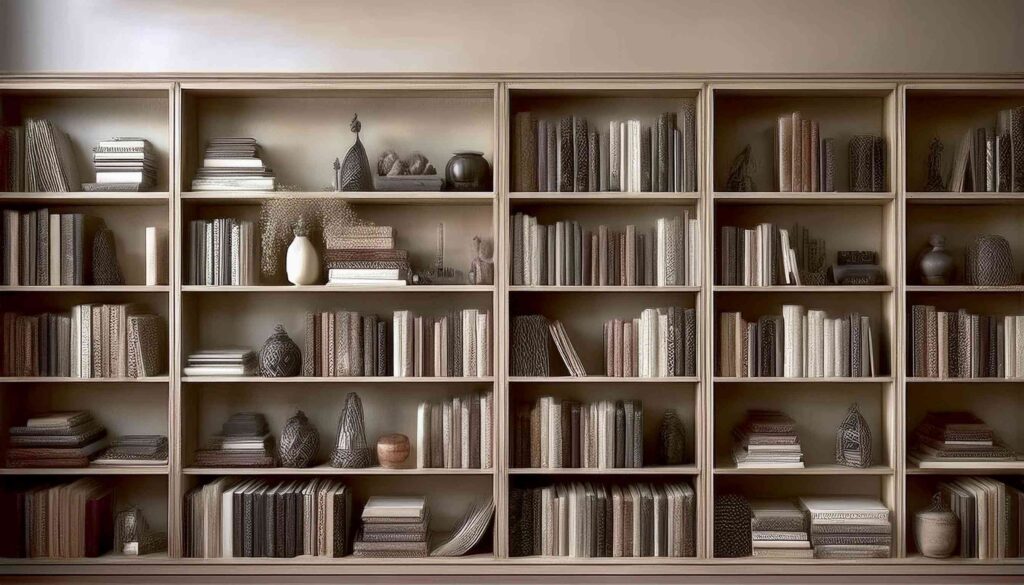
「相続時精算課税制度」とは、贈与税と相続税を連動させ、贈与時に特別控除額2,500万円までは贈与税がかからず控除額を超える部分に対して贈与税が課される制度です。
贈与者が亡くなった際には、贈与財産を相続財産に加算し相続税を計算します。つまり、既に納めた贈与税は相続税から控除されます。
例えば、子供に親が2,500万円を贈与し相続時精算課税制度を使った場合、子供は贈与税を支払う必要はなくなります。
しかし、親が亡くなった際には、親の遺産を含め、この制度で贈与した2,500万円を足した分が相続税の対象となります。
例えば、残りの遺産が2,000万円の場合の相続税の対象金額は、
2,500万円(贈与分)+残りの遺産2,000万円→相続税の対象は4,500万円になります。
この制度は節税効果は低いものの、次世代への財産移転を早める手段として検討する価値があります。
ちなみに親から2,500万円を贈与され、何の特例も使わないで贈与税をざっくり計算した場合、贈与税は945万円になります(税率が50%・控除額が250万円)。
国税庁ホームページ参照「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm(20240815)
適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
国税庁ホームページ参照「No.4103 相続時精算課税の選択」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm(20240815)
法律改正
令和5年度税制改正により租税特別措置法の一部が改正され年110万円の基礎控除が創設されました。
また、特別控除の適用がある場合はその金額を控除した残額に20%の税率を乗じて贈与税を算出します。
国税庁ホームページ「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」参照https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf(20240815)
メリットとデメリット、注意点

相続時精算課税制度を利用しようと考えた場合、必ずメリットとデメリットを考慮し、この制度の適用を慎重に検討することが重要です。
メリット
早期にまとまった資産を非課税で贈与可能
相続時精算課税制度を利用すれば、特別控除額2,500万円まで、子や孫にまとまった資産を非課税で贈与することができます。この制度を活用することで、財産を確実に次世代へ移転することが可能です。
相続税の軽減効果
この制度で贈与した財産は、相続時に贈与時の評価額で相続財産に加算されます。そのため、将来的に値上がりが見込まれる財産を贈与することで、相続税の負担を抑える効果が期待できます。
デメリット
小規模宅地等の特例が適用されない
この制度を利用して贈与された宅地等には、「小規模宅地等の特例」が適用されません。この特例は、居住用などの宅地が相続される際に、一定の要件を満たすことで評価額を80%減額するものですが、この制度を選択すると利用できません。
小規模宅地の特例をご存じでしょうか?一定の要件に当てはまれば敷地の相続税評価額を最大80%引き下げることができる特例です。こちらの「家族に安心を!小規模宅地の特例を理解しよう」という記事では、小規模宅地等の特例の内容や適用要件の説明、注意点と良くある質問を解説しました。相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。この記事を読むことで、小規模宅地の特例を正しく理解し、相続手続きの準備を万全に整える手助けとなります。
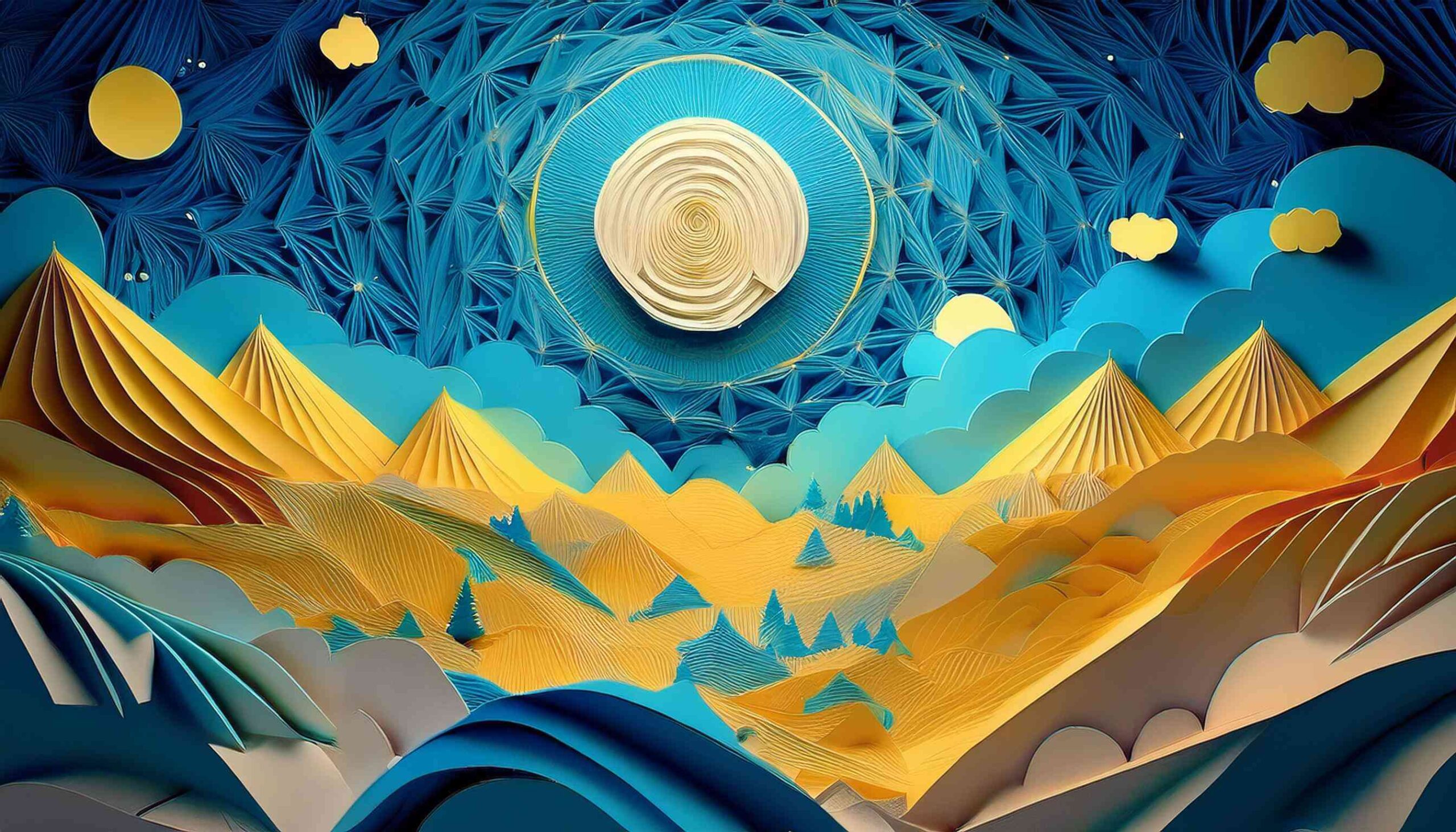
選択の撤回ができない
相続時精算課税制度を一度選択すると、撤回することはできません。また、この制度を利用している間は、年間110万円の贈与税非課税枠を持つ「暦年贈与」との併用ができないため、柔軟な贈与計画が難しくなる可能性があります。
注意点
必要書類の提出
相続時精算課税制度を利用するには、選択届出書などの必要書類を提出する必要があります。
累計2,500万円超過時の贈与税
累計で2,500万円を超える贈与に対しては、超過分に対して20%の贈与税が課されます。
暦年課税制度への戻れない
一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れません。年110万円を超える贈与には贈与税の申告が必要で、制度の判断や計算が複雑になる点も考慮すべきです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
相続時精算課税制度は、早期に資産を移転するための有効な手段ですが、誤った理解や準備不足によって、後々大きな問題を引き起こす可能性もあります。
本記事では、この制度の内容やメリット・デメリット、注意点について詳しく解説しました。
相続の準備を怠ることは、家族にとって大きな負担となり、スムーズな手続きを難しくする原因となります。しかし、適切な知識を持ち、事前に対応することで、相続手続きを円滑に進め、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
ぜひこの記事を参考にして、相続手続きの準備や対策にお役立てください。