
二次相続をご存じですか?
一次相続に比べて、二次相続は税金負担が大きくなる可能性が高く、家族間でのトラブルも起きやすいとされています。
しかし、「今はまだ大丈夫」と思って準備を怠ると、結果的にご家族が負担を強いられる事態になるかもしれません。
たとえば、一次相続で配偶者が多くの遺産を相続した場合、二次相続ではその遺産のほとんどが課税対象となり、相続税が大幅に増加することがあります。
また、明確な遺言書や計画がないと、親族間で遺産分割がまとまらず、深刻な対立に発展するケースも少なくありません。
事前に二次相続を理解して、しっかりとした準備をすることで、これらのリスクを防ぎ、スムーズに相続手続きを進めることができます。
本記事では、二次相続の基本知識を解説し、一次相続との違い、さらに事前に注意すべき点や具体的な対策方法について詳しくお伝えします。
この記事を読むことで、相続に関する不安を解消し、大切な家族をサポートするための一歩を踏み出すことができるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
二次相続とは

相続には大きく分けて「一次相続」と「二次相続」の2種類があります。
それぞれは何を指すのでしょうか?
ここでは、特に二次相続についてこの記事では詳しく解説します。
一次相続と二次相続の違い
一次相続とは、夫婦どちらか一方が亡くなった際に発生する相続のことです。一方、二次相続は、一次相続の後にもう一方の配偶者が亡くなった際に発生します。
たとえば、父親が亡くなった後に母親が亡くなる場合、父親の相続が「一次相続」、母親の相続が「二次相続」となります。
二次相続が重要な理由
二次相続は、一次相続に比べて税金の負担が増える可能性が高く、また家族間のトラブルが起きやすい特徴があります。以下にその主な理由を解説します。
配偶者の税額軽減が使えない
一次相続では、配偶者が相続する財産について「配偶者の税額軽減」の特例が適用され、多くの場合、相続税を大幅に抑えることができます。
しかし、二次相続では配偶者がすでに他界しているため、この特例を利用することができません。結果として、子どもたちが相続税を負担する必要があり、税額が増える傾向にあります。
基礎控除が少ない
相続税の課税対象となる遺産の額を減らす「基礎控除」は、相続人の数に応じて計算されます。
二次相続では、配偶者が亡くなっているため相続人が減少し、基礎控除額も一次相続時より低くなります。そのため、課税対象となる遺産額が増える場合があります。
小規模宅地等の特例が使えない場合がある
自宅や事業用不動産を相続する際に適用できる「小規模宅地等の特例」も、二次相続では利用できないケースがあります。たとえば、残った配偶者が法定相続人である子供と同居していないなど一定の条件を満たしていなければ、二次相続ではこの特例が適用されない可能性があります。その結果、課税額が大きくなることがあります。
配偶者がもともと所有していた財産が合算される
一次相続後、配偶者が所有していた財産も二次相続の課税対象に含まれます。これにより、相続税の課税額がさらに増加することがあります。
遺産分割協議が合意に至らない場合も
二次相続では相続人が子どもだけになる場合が多く、遺産分割協議がまとまらずトラブルに発展する可能性があります。それぞれの相続人が異なる意見を持つことが多いため、合意形成に時間がかかり、結果として相続手続きが長引くこともあります。
準備と対策
二次相続は、相続税の負担や家族間のトラブルが発生しやすい特徴があります。そのため、一次相続の段階で二次相続を見据えた準備と対策を講じることが重要です。
以下に、具体的な準備と対策をご紹介します。
すべての遺産を配偶者に相続しない
一次相続で遺産の全てを配偶者が相続すると、配偶者の税額軽減が適用され、一次相続時の税金は軽減されます。
しかし、その分二次相続時の課税対象となる遺産が増加し、相続税が高額になる可能性があります。一部の遺産を子供に相続させることで、二次相続時の税負担を分散できます。
生前贈与の活用
生前贈与を計画的に活用することで、相続財産の総額を減らし、税負担を軽減できます。年間110万円までの贈与は非課税で行えるため、早めに取り組むことが効果的です。また、今の税制優遇策での教育資金や結婚資金の贈与特例を利用することで、さらに節税が可能です。
同居する子供が自宅を相続
一次相続で自宅を同居する子供に相続させると、小規模宅地等の特例を適用できます。
この特例により、自宅の評価額を最大80%減額できるため、相続税を大幅に軽減することが可能です。
生命保険を活用する
生命保険金は、法定相続人1人あたり500万円まで非課税になる特例があります。ただし、配偶者が受取人だと、二次相続の際にも相続税の課税対象になるので注意が必要です。保険金受取人を子供にすることで、この特例を活用できます。また、生命保険は現金として早めに受け取れるため、葬式費用などの支払いとしても役立ちます。
比較的値上がりしそうな財産を一次相続で子供に相続
株式や不動産など、将来的に価値が上がる可能性が高い財産は、配偶者に相続させてしまうと、相続財産額が増えるため一次相続の段階で子供に相続させると良いでしょう。これにより、二次相続での相続財産の額が増えることを抑えることができます。
相次相続控除の適用
一次相続と二次相続が10年以内に発生した場合、「相次相続控除」を適用できます。
これは、短期間での相続による税負担を軽減する制度です。二次相続を想定しておき控除が適用できる条件を確認しておくと良いでしょう。
家族で話し合いを行う
二次相続はあるものと考え、生前、遅くても一次相続時から家族間で十分に話し合いを行うことが大切です。
誰がどの財産を相続するのか、配偶者がどのように生活していくのかを共有することで、遺産分割におけるトラブルを未然に防げます。
配偶者の住居と生活費をシミュレーションする
一次相続後、配偶者が安心して暮らせるよう、住居と生活費について具体的にシミュレーションしておきましょう。
配偶者に必要な資産を確保しつつ、二次相続の負担を抑えるバランスを考えることが重要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
本記事では、二次相続の基本知識を解説し、一次相続との違い、さらに事前に注意すべき点や具体的な対策方法について詳しくお伝えしました。
一次相続に比べて、二次相続は税金負担が大きくなる可能性が高く、家族間でのトラブルも起きやすいとされています。
しかし、「今はまだ大丈夫」と思って準備を怠ると、結果的にご家族が負担を強いられる事態になるかもしれません。
事前に二次相続を理解して、しっかりとした準備をすることで、これらのリスクを防ぎ、スムーズに相続手続きを進めることができます。
この記事を参考にして頂き、相続に関する不安を解消し、大切な家族をサポートするための一歩を踏み出してみてください。
配偶者控除で本当に相続税がゼロになるの?相続税対策が複雑だと感じる方も多く、適切な知識がないと損をしてしまうケースも少なくありません。ご家族の相続手続きをスムーズに進めたいと思っている方ほど、この控除を正しく理解することが重要です。こちらの記事では、配偶者控除の基礎知識、計算方法、そして、事前に知っておいた方がよい注意事項やよくある質問まで、わかりやすく解説しました。

自分の相続対策や準備、身近な人の相続手続きをサポートしようとしても、基本的な知識がないとスムーズに進められず、ストレスを感じられるかもしれません。実際、相続税の基礎控除や課税仕組みを理解していないと、適切な相続対策ができずに余分な税金を払ってしまうケースが少なくありません。この記事では基礎控除について詳しく解説しました。ぜひ、この記事を、相続準備のヒントとしてお役立てください。

小規模宅地の特例は相続手続きにおいて重要です。なぜなら、多くの方にとって大きなメリットをもたらす可能性があるからです。しかし、具体的にどのような特例の内容であり、どんなことに注意すれば良いのでしょうか?この記事では、小規模宅地等の特例の内容や適用要件の説明、注意点と良くある質問を解説しました。相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。この記事を読むことで、小規模宅地の特例を正しく理解し、相続手続きの準備を万全に整える手助けとなります。
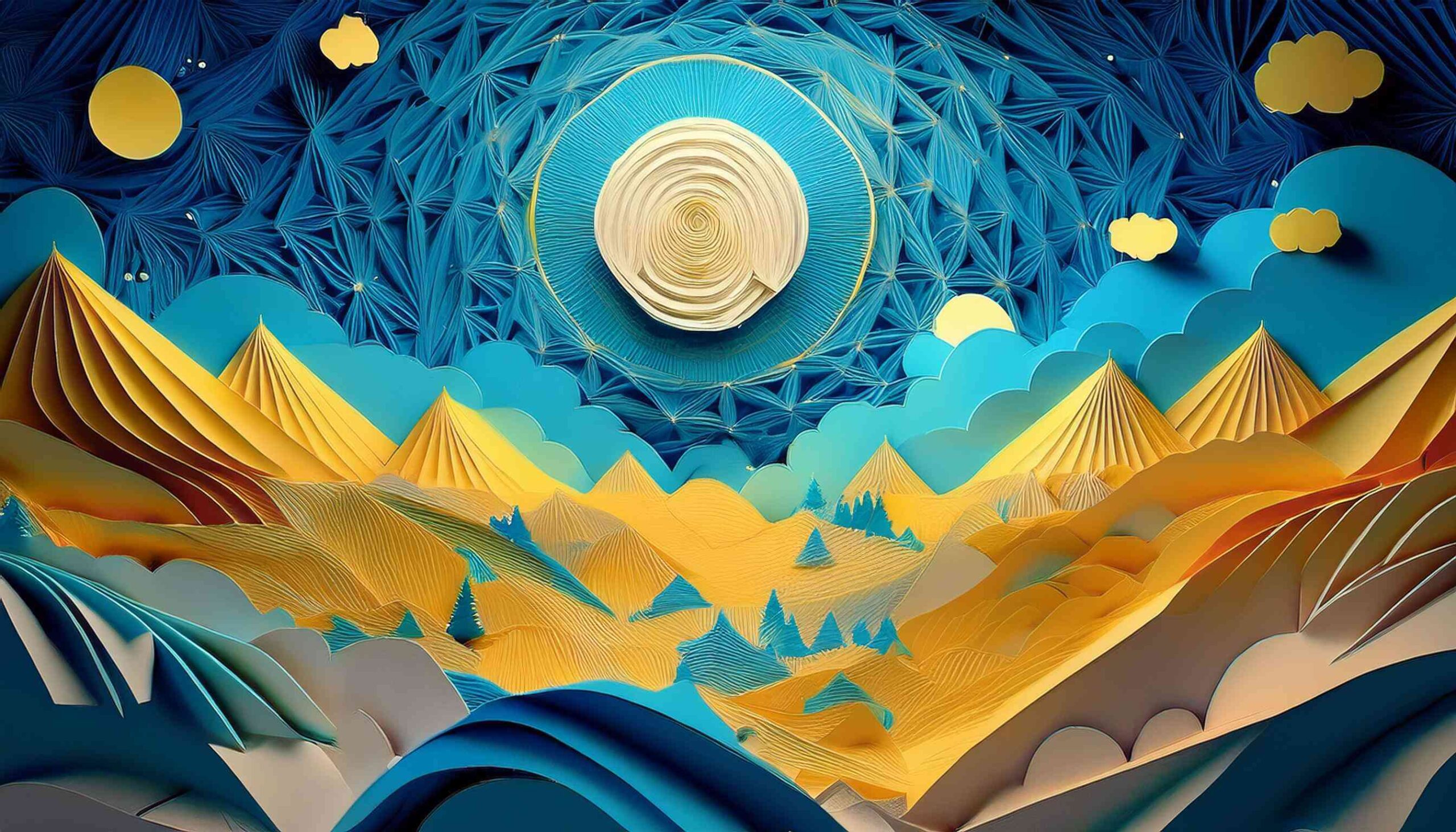
故人の生命保険を受け取った場合は相続税が掛かるのか?これは多くの人が気になる疑問です。事前に知っておいたほうがいいことは何かあるのか?この記事では、生命保険と相続税の関係や基礎知識を解説し、今から注意しておきたいポイントなどを詳しく説明します。適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。ぜひこの記事を、相続手続きのヒントとしてお役立てください。
