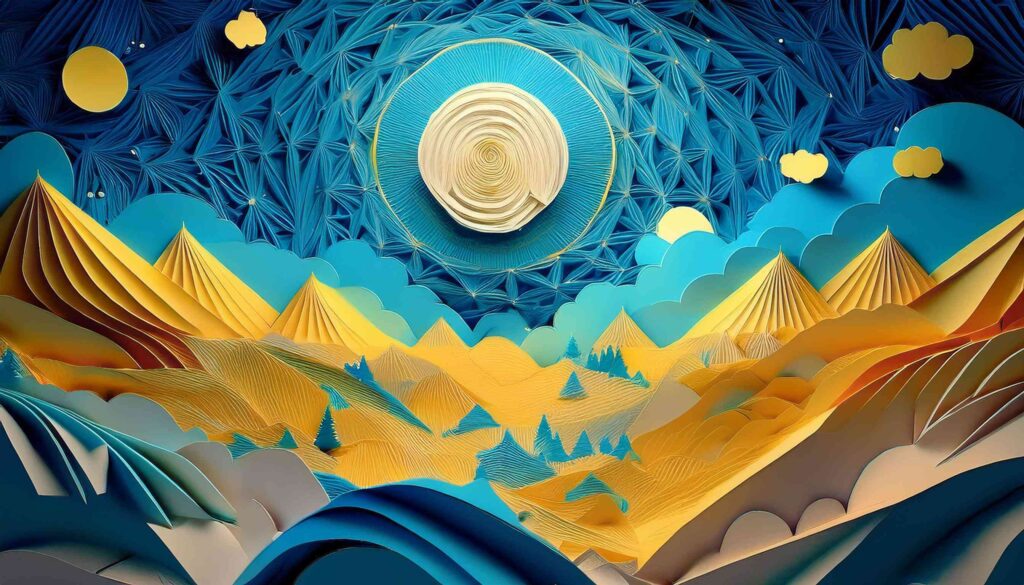
小規模宅地の特例があることをはじめて知りましたか?
相続手続きにおいて重要なこの特例は、多くの方にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。
しかし、具体的にどのような特例の内容であり、どんなことに注意すれば良いのでしょうか?
この記事では、小規模宅地等の特例の内容や適用要件の説明、注意点と良くある質問を解説します。
相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
この記事を読むことで、小規模宅地の特例を正しく理解し、相続手続きの準備を万全に整える手助けとなります。
ぜひ、この記事を、相続準備や対策のヒントとしてお役立てください。
小規模宅地等の特例とは

相続税の負担を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」とは、故人が住んでいた自宅の敷地を一定の親族が相続した場合に、その敷地の相続税評価額を最大80%引き下げることができる特例です。
この特例を活用することで、相続税の負担を大きく抑えることが可能となります。
例えば、評価額が3000万円の住宅敷地があった場合、この特例の適用を受けることで、その敷地の評価額が600万円にまで引き下げられ、課税対象となる相続税額が大幅に減少します。これは、家族が住み慣れた家を手放さずに済むようサポートする大変重要な制度です。
ただし、この特例を適用するためには一定の条件を満たす必要があります。例えば、相続人が継続してその土地を使用する意志があるか、被相続人と同居していたかなどの要件があり、これらを事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
この特例を正しく理解し、適用条件を満たすための準備をすることで、相続手続きをよりスムーズに進め、大切な家族を経済的にしっかりとサポートすることができます。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができますが、この特例を適用するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
特に、一般の住宅では330㎡までの面積が対象となり、取得者については故人の配偶者や同居していた親族、さらには同居していなかった親族など、それぞれのケースで異なる適用要件があります。
これらの具体的な適用要件について詳しく解説していきますので、相続手続きを進める際の参考にしてください。
取得者
故人の 配偶者
特別な要件なし
同居親族
相続開始直前から故人の建物に居住していた親族のこと、ただし相続税の申告期限まで引き続き建物に住み続け、かつ、その宅地等を所有していることが要件となっています。親が亡くなる直前だけ同居しただけでは適用されません。
同居親族以外(家の所有なし)
主に下記の要件があります。
- 故人に配偶者がいない
- 同居相続人がいない
- 相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していない
- 相続開始時から相続税の申告期限までその宅地等を有している
- 相続開始時において故人もしくは相続人が日本国内に住所がある、又は、相続人の住所が日本になくても日本国籍がある
など
詳しくは国税庁ホームページ「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」をご確認下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm(20240812)
また、事前に最寄りの税務署で税務相談も出来ます。もし、ご利用される場合は予約が必要な場合が多いので事前にご連絡して下さい。
金沢税務署電話相談センター(金沢市)
076-261-3221
松任税務署(野々市市・白山市)
076-276-2345
国税庁のホームページでも、チャットボットやタックスアンサーなどで国税に関する疑問や質問などを調べることができますので是非ご活用ください。
小規模宅地等の特例の計算例
※①も②も故人が相続開始前の直前において居住していた家屋の敷地になります。
①特定居住用宅地・評価額5000万円、面積300㎡の場合
・特例によって評価減できる金額
5000万円×(300㎡÷300㎡)×80%=4000万円
・評価額
5000万円→1000万円
②特定居住用宅地・評価額4000万円、面積400㎡の場合
・特例によって評価減できる金額
7000万円×(330㎡÷400㎡)×80%=5775万円
・評価額
7000万円→1225万円
良くある質問と注意点

相続手続きに多くの業者が関わる中で、イシトチ不動産の最大の強みは「誠実な対応」です。
代表である私自身も、父の相続手続きを経験し、その過程で数々の困難に直面しました。この経験を通じて、事前に準備しておくべきことや注意すべきポイントがいくつもあることを痛感しました。
相続手続きにおける不安や疑問に対して、誠実に向き合いながらサポートするため、私たちはお客様一人ひとりの事情をしっかりとヒアリングし、それぞれのニーズや要望に応じた個別対応を行うことにこだわっています。
以下に、お客様からよく寄せられる質問とその回答をピックアップしました。これらが少しでもお役に立てれば幸いです。
もし、他にご質問があれば、ぜひ下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。
相続税の申告は必要ですか?
小規模宅地等の特例を受けるためには相続税申告は必要です。
相続税申告時の添付書類は何ですか?
被相続人と同居している場合は、特例の適用を受ける宅地等に自己が住んでいることを明らかにする書類が必要になります。また、被相続人と同居していない場合は、相続開始前3年以内の住所等を明らかにする書類などが必要です。
詳しくは下記の国税庁ホームページ相続税の申告のしかた(令和5年分用)(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類をご確認下さい。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E11.pdf(20240812)
また、共通の書類としては、
- 法定相続情報一覧図の写し又は被相続人、全ての相続人の戸籍の謄本
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
等は取得者に限らず必要になります。
同居期間の基準はありますか?
同居期間について制約はありません。
二世帯住宅の場合はどうなりますか?
区分所有登記されているかどうかがポイントです。親ひとりの単独名義か、親子の共有名義であれば、小規模宅地等の特例が受けられます。建物構造上区分されているかどうかは関係ありません。
故人が老人ホームに入居していた場合は?
故人が亡くなる直前に要介護認定、要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたことなど一定の要件が必要になりますが可能です。その際には、必要書類が複雑になるため注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用して贈与された土地は適用できますか?
相続時精算課税制度を利用して贈与された土地等は小規模宅地等の特例の適用対象外となります。
住民票では故人と一緒でしたが同居はしていませんでした。適用できますか?
同居の実態がなければ特例は使えません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
小規模宅地の特例は相続手続きにおいて重要で、多くの方にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。
この記事では、小規模宅地等の特例の内容や適用要件の説明、注意点と良くある質問を解説しました。
相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
この記事を読むことで、小規模宅地の特例を正しく理解し、相続手続きの準備を万全に整える手助けとなります。
この記事が、相続手続きのヒントとしてお役立ていただければ幸いです。小規模宅地の特例を活用して、スムーズでトラブルのない相続手続きや準備を目指しましょう。