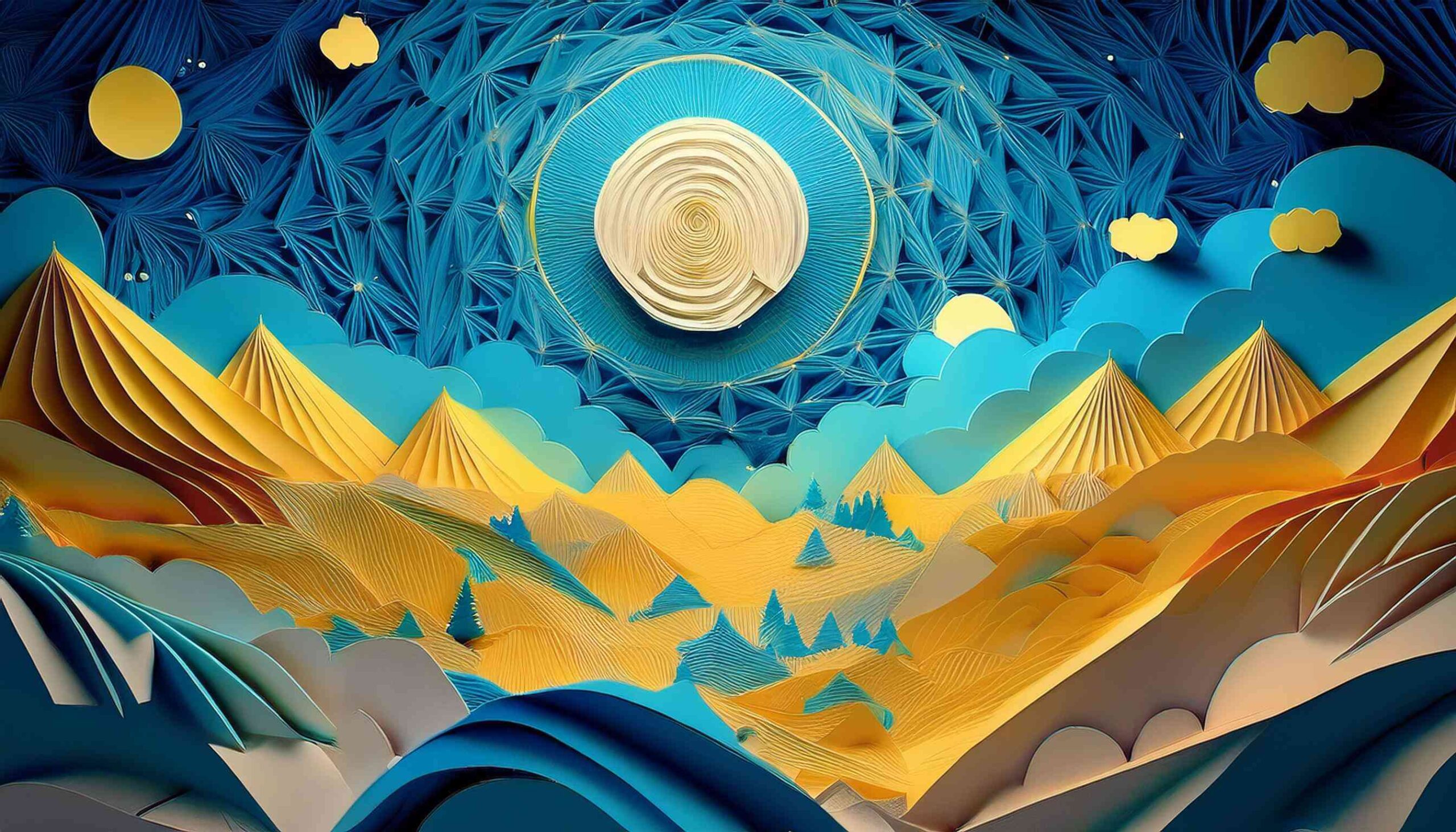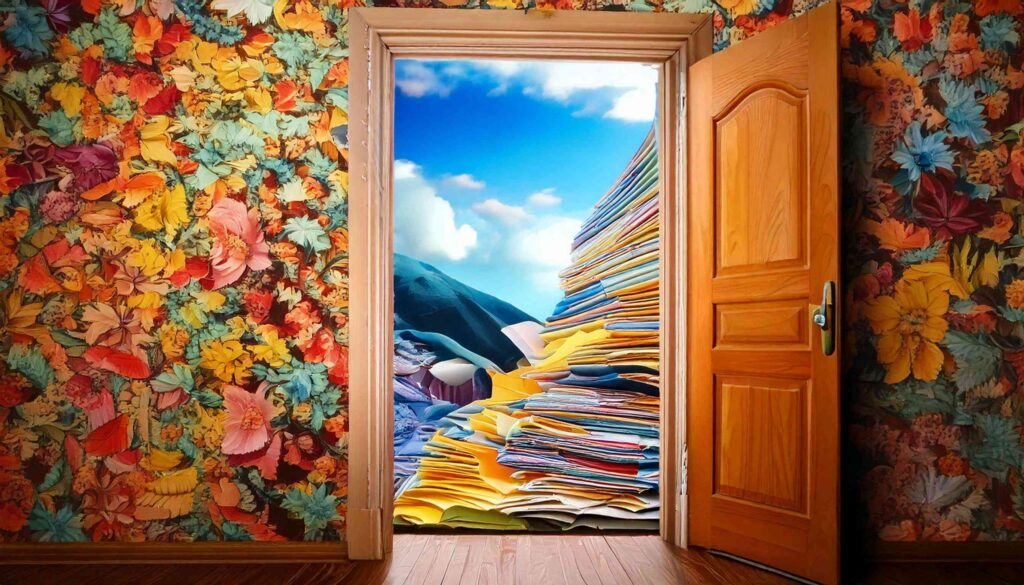
相続税の計算方法や準備に不安を感じていませんか?
特に、相続税がどのくらいかかるのか、手元に残る資産がどれくらいなのかを把握しないまま亡くなってしまうと、思わぬ税負担が発生し、残った家族に資産をスムーズに引き継げなくなる恐れもあります。
実際に相続税についてしっかりと準備しておかないと、予想以上の税額を支払う必要も出てくることもあります。
相続における税額の目安を理解してないために、事前に対策を講じない場合に後から家族が困惑してしまうケースも少なくありません。
この記事では、相続税の基本的な知識や計算方法についてわかりやすく解説し、相続税早見表の活用方法や具体的な対策・注意点についても触れていきます。
事前に知っておきべきポイントを押さえることで、安心して相続の準備を進め、将来、大切な家族が困らないようにしておきましょう。
ぜひこの記事を参考に、相続準備をスムーズに進めるためのヒントにしてください。
相続税はいくら?

相続税は相続財産の金額に応じて課される税金です。
具体的にどれくらいの金額が相続税として必要になるかは、相続財産の総額や法定相続人の数によって異なります。
まずは相続税の計算方法や基礎控除について、具体的に見ていきましょう。
計算方法
相続税の計算は相続財産の総額を計算し、そこから基礎控除を引いた金額に税率を掛けて算出されるのが基本です。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円(3000万円+600万円×3)となります。
この基礎控除額を超える部分に対して相続税が課されます。
相続財産の金額
相続財産には、不動産や預貯金、株式、生命保険など、さまざまな資産が含まれます。
これらを全て合算し相続財産の総額を算出します。
負債がある場合は、それも差し引くことができます。
基礎控除
基礎控除とは、相続税の計算において課税対象となる金額を減らすための控除額です。
先述の通り、基礎控除額は3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えた額で計算されます。
この基礎控除のおかげで、全ての相続に対して相続税が課されるわけではなく、多くの家庭では基礎控除内に収まるケースも少なくありません。
また、基礎控除額は法定相続人の数によって決まります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除は3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円です。
この基礎控除を超える財産に対して相続税が課されることになります。
相続税早見表
基礎控除を超える財産に対して相続税が課されることになるため、基礎控除以下の相続財産であれば相続税を払う必要はありません。
相続税早見表は相続財産の金額と法定相続人の数に応じた基礎控除を目安に確認するための表です。
相続税早見表により、相続税の概算額を把握することができ、相続税の準備や対策を効率的に行う助けになります。
また、この表を使うことで、具体的な計算をすることなく、おおよその相続税額を把握することもできます。
例えば、相続財産が5,000万円ある場合、法定相続人が2人ならどのくらいの相続税が必要かを一目で確認できます。相続税の見通しを立てることで、相続に関する不安を減らし計画的な相続準備や対策が可能になります。
ぜひ、ご参考にしてください。
この「早見表」は、配偶者の税額軽減のみ適用しています。また、法定相続人が法定相続分通りに相続した場合の金額です。
※相続税早見表(単位:万円)
| 相続財産の価額 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 |
| 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000 | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 6,000 | 90 | 60 | 30 | 0 |
| 7,000 | 160 | 113 | 80 | 50 |
| 8,000 | 235 | 175※ | 137 | 100 |
| 9,000 | 310 | 240 | 200 | 162 |
| 10,000 | 385 | 315 | 262 | 225 |
| 12,000 | 580 | 480 | 402 | 350 |
| 14,000 | 780 | 655 | 577 | 500 |
| 16,000 | 1070 | 860 | 767 | 675 |
参考:基礎控除額(配偶者含む)
子供1人の場合の基礎控除額 4200万円
子供2人の場合の基礎控除額 4800万円
子供3人の場合の基礎控除額 5400万円
子供4人の場合の基礎控除額 6000万円
※計算例
相続財産の価額 8,000万円 配偶者、子2人の場合
①課税遺産額の計算 8,000万円ー4,800万円(基礎控除額)=3,200万円
②相続税総額の計算
配偶者(1/2)1,600万円×15%ー50万円=190万円(A)
子供(1/4)800万円×10%=80万円 二人分で160万円(B)
(A)+(B)=350万円
③各相続人の相続税額の計算
配偶者:350万円×1/2=175万円
子供2人分::350万円×1/2=175万円
参考:相続税の速算表
- 1,000万円以下 税率10% 控除額0円
- 3,000万円以下 税率15% 控除額50万円
- 5,000万円以下 税率20% 控除額200万円
- 1億円以下 税率30% 控除額700万円
- 2億円以下 税率40% 控除額1,700万円
- 3億円以下 税率45% 控除額2,700万円
- 6億円以下 税率50% 控除額4,200万円
- 6億円超 税率55% 控除額7,200万円
※子供が増えれば基礎控除額が大きくなります。また、相続財産の価額がその控除額以下であれば相続税は掛かりません。※配偶者がいない場合の2次相続の早見表については下記をご参照ください。※相続税額は万円未満を四捨五入しています。
対策と注意
実際には相続税の負担を軽減できる特例が存在します。これらの特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。ここでは主な特例をご紹介します。
配偶者の税額軽減
配偶者に対する相続税の軽減措置では、配偶者が取得する財産に対する相続税が大幅に減額されるか、場合によっては非課税となることがあります。この特例により、配偶者の生活を守ることができます。
未成年者控除
相続税の負担を軽減するための特例制度の一つに「未成年者控除」があります。この控除は、相続人が未成年である場合に、将来の生活資金を考慮して相続税を減額するためのものです。
障害者控除
「障害者控除」は、相続人が障害者である場合に利用できる相続税の軽減制度です。今後の障害者の生活のために、将来的な経済的負担を軽減する目的で設けられています。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地に対する相続税評価額を大幅に減額できる制度です。これにより、相続財産の評価額を抑え、相続税の負担を軽減することが可能です。
二次相続について
相続対策では、一次相続だけでなく、その後の二次相続も考慮することが重要です。
例えば、配偶者が全ての財産を相続した場合、その後配偶者が亡くなった際の二次相続で相続税が多くかかることがあります。そのため、一次相続の段階での分割方法が重要です。
※相続税早見表(単位:万円)
| 相続財産の価額 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 |
| 4,000 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000 | 160 | 80 | 20 | 0 |
| 6,000 | 310 | 180 | 120 | 60 |
| 7,000 | 480 | 320 | 220 | 160 |
| 8,000 | 680 | 470 | 330 | 260 |
| 9,000 | 920 | 620 | 480 | 360 |
| 10,000 | 1220 | 770 | 630 | 490 |
| 12,000 | 1820 | 1160 | 930 | 790 |
| 14,000 | 2460 | 1560 | 1240 | 1090 |
| 16,000 | 3260 | 2140 | 1640 | 1390 |
参考:基礎控除額(配偶者含まない)
子供1人の場合の基礎控除額 3600万円
子供2人の場合の基礎控除額 4200万円
子供3人の場合の基礎控除額 4800万円
子供4人の場合の基礎控除額 5400万円
※配偶者分がなくなると相続税額が顕著に高くなります。※相続税額は万円未満を四捨五入しています。
まとめ
いかがだったでしょうか?
相続税は、相続財産の金額や法定相続人の数に応じて変動します。
相続税早見表を活用することで、相続税の概算を把握し、必要な対策を早めに取ることが可能です。
また、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除、小規模宅地等の特例など、負担を軽減するための制度をうまく活用することで、相続税の負担を抑えることができます。
相続税対策の準備は早めに取り組むことで、将来の安心に繋がりますので、ぜひ検討してみてください。
株式会社イシトチ不動産では、代表の小川が経験してきた知識を活かして、皆さまの不安を解消し、最適な相続対策をご提案しています。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの大切な資産とご家族を守るために、私たちがお手伝いいたします。
▼詳細はこちらから
こちらからお申込み下さい
2営業日以内にご連絡致します。また、ご相談いただいた内容に誠実に向き合い、お客様のご意向を最優先に考えたサポートを心がけています。安心して、まずはお話をお聞かせください。
株式会社イシトチ不動産では、相続に関する知識や事例を詳しくご紹介する記事を多数ご用意しています。
分かりやすい内容を心がけておりますので、相続初心者の方でも安心してご参考いただけます。
どの情報もあなたがご家族のためにより良い相続準備を進めるためのお役に立つはずです。気になる内容がございましたら、ぜひご覧ください!
【関連記事】
配偶者控除で本当に相続税がゼロになるの?相続税対策が複雑だと感じる方も多く、適切な知識がないと損をしてしまうケースも少なくありません。ご家族の相続手続きをスムーズに進めたいと思っている方ほど、この控除を正しく理解することが重要です。こちらの「相続税がゼロに?知っておきたい配偶者控除」では、配偶者控除の基礎知識、計算方法、そして、事前に知っておいた方がよい注意事項やよくある質問まで、わかりやすく解説しました。

相続で未成年者が関わる場合、「相続税の未成年者控除」を活用することで大きな負担を軽減できることをご存知でしょうか? この控除を知らないままでいると、思いがけない相続税負担が発生することがあります。また、控除の適用には事前の理解が必須です。こちらの「相続税負担を軽減する未成年者控除の基礎知識」では、未成年者控除の基礎知識や計算方法、注意点まで詳しく解説しました。

家族に障害のある方がいる場合、相続税の「障害者控除」を使うことでご心配を軽減できることをご存知でしょうか?しかし、控除の適用を受けるには特定の条件や準備が必要です。こちらの「相続税の障害者控除とは?大切な家族を守るための知識」では、相続税の障害者控除について、その概要や計算方法、必要書類、注意点を解説しました。大切なご家族を守り、円滑な相続をサポートするために、ぜひご参考にして下さい。
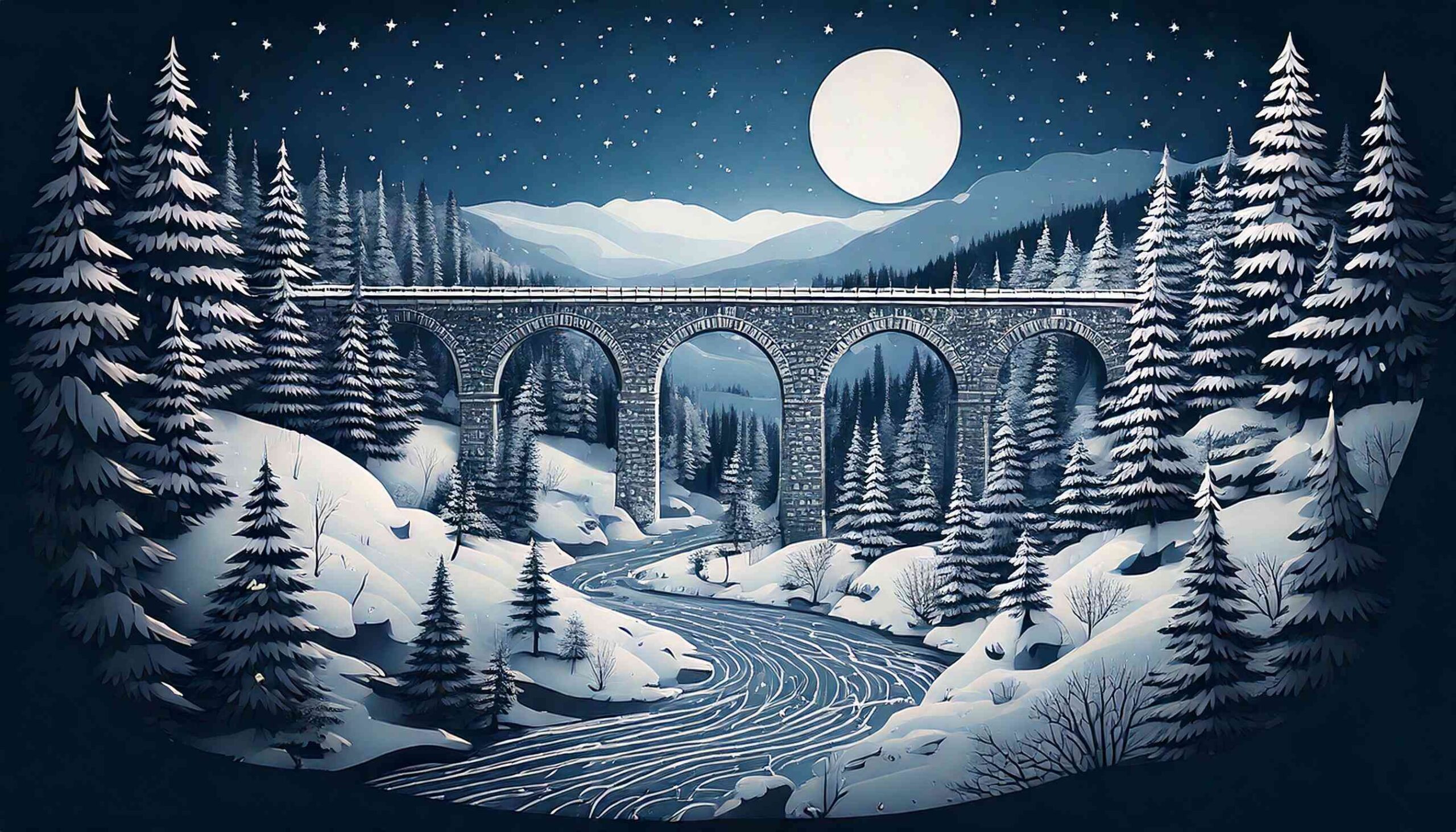
小規模宅地の特例は相続手続きにおいて重要です。なぜなら、多くの方にとって大きなメリットをもたらす可能性があるからです。しかし、具体的にどのような特例の内容であり、どんなことに注意すれば良いのでしょうか?こちらの「家族に安心を!小規模宅地の特例を理解しよう」では、小規模宅地等の特例の内容や適用要件の説明、注意点と良くある質問を解説しました。