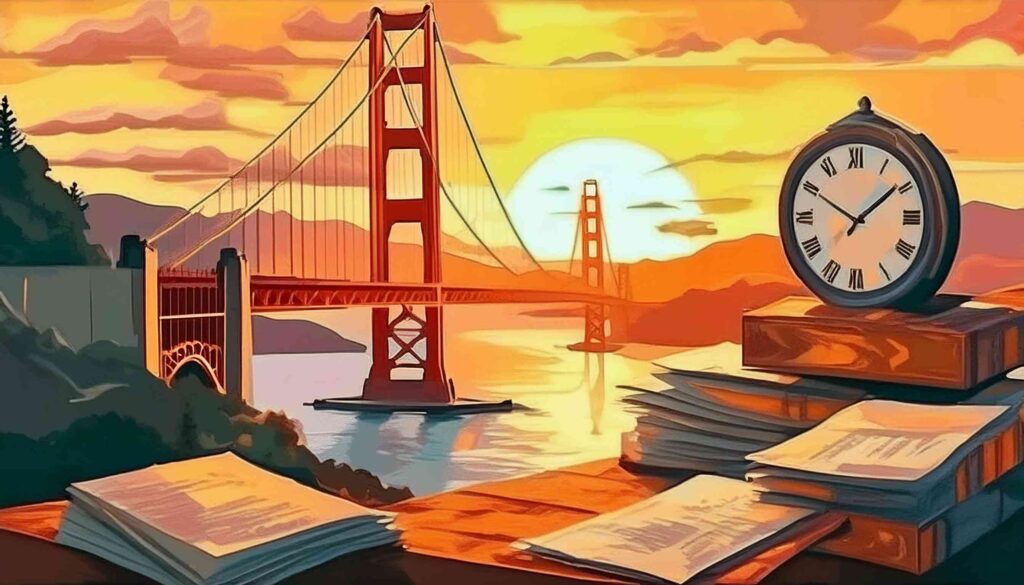
相続税の支払いには期限があります。
家族に負担をかけないために、今からできることは何でしょうか?
相続税の申告と納税は、財産の持ち主が亡くなった日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
期限に遅れそうな場合、どう対処すればよいのでしょうか?
この記事では、相続税の申告と納付期限に関する詳しい情報と、今からできる準備を紹介します。
これにより、家族に負担をかけずにスムーズに相続準備を進めることができます。
この記事を身近な人への相続手続きやご自分の相続準備のヒントにして下さい。
相続税の申告期限・納付期限はいつまで?
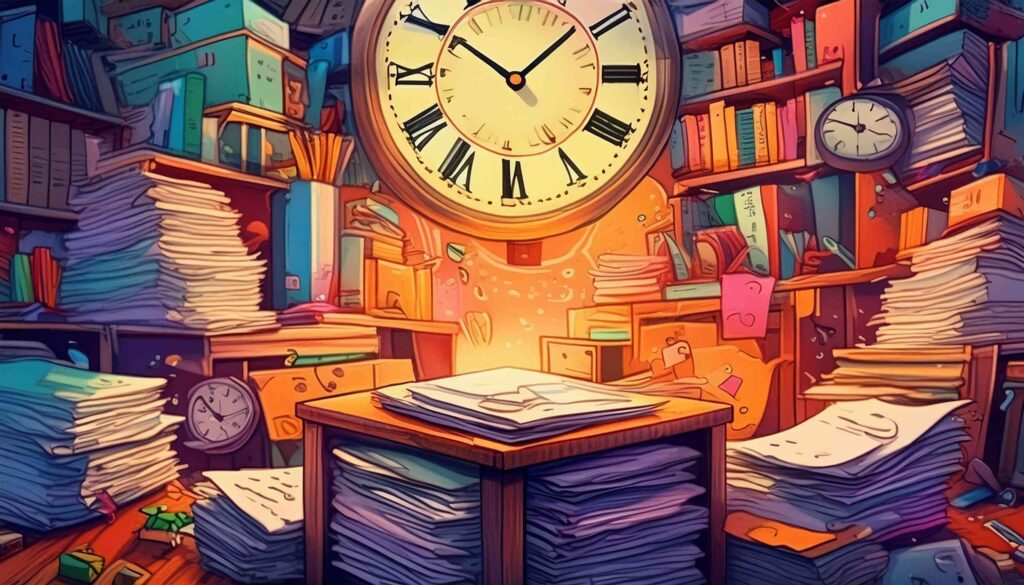
相続税の申告と納付は、相続が発生した日から10カ月以内に行わなければなりません。この期限を守らないと、ペナルティが発生する可能性があります。
申告、納税が必要な場合
相続税の申告と納税が必要な場合は相続財産の総額が基礎控除額を超える時です。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えた金額です。
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
つまり、法定相続人が3人の場合は相続財産が4,800万円を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。
基礎控除額以内の相続財産であれば申告も納税も必要がありません。
相続税の申告と納付までの流れ
相続税の申告と納付までには、いくつかの重要なステップがあります。
具体的な流れを説明します。
相続人・遺言の有無の確認
まず、相続が発生した際には、法定相続人を確認し、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。
相続財産の調査
次に、相続財産の調査を行います。これは、故人が所有していた不動産、預貯金、株式、債務などを含む全ての財産を把握する重要な内容です。この調査結果が相続税の申告額に直結します。
相続放棄または限定承認の意思表示
相続財産の調査が終わった後、相続人は相続放棄や限定承認を行うかどうかを決定します。相続放棄は、相続権を放棄することで、限定承認は、相続した財産の範囲内で債務を負うことを承認する手続きです。これらの意思表示は、相続開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
準確定申告
故人が個人事業主や会社経営者であった場合、死亡日から4カ月以内に準確定申告を行わなければなりません。これは、故人の最終的な所得税の申告です。
遺産分割協議
法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決定します。遺産分割協議書を作成し、全員の署名と押印をもって成立します。この協議が円滑に進むことが、その後の申告や納税手続きに大きく影響します。
申告書の提出・納税
最後に、相続税の申告書を作成し、相続開始から10カ月以内に税務署に提出します。同時に、相続税を納税します。納付を同時にしなくてもいいですが申告と納付の期限は同じですので注意が必要です。
支払い方法
相続税は原則として、金銭により一括して納める必要があります。
納付の方法には、銀行など金融機関やコンビニ、クレジットカード、税務署の窓口などで支払う4つのパターンがあります。
一部のコンビニエンスストアでも相続税を支払うことができ、この方法は利便性が高く、銀行の営業時間内などにいけない忙しい方におすすめです。
また、インターネットを利用してクレジットカードで納税することもできます。ポイント還元などのメリットがある反面、手数料がかかる場合もあるので注意が必要です。
もし、手続きに不安がある場合、税務署の窓口に行って納付する方法を選択すれば、税務署の職員に直接相談できます。
注意点としては、相続税の納付義務は、財産を相続した相続人が負担するので、相続人が複数いる場合、それぞれの相続人ごとに納付書を作成し、個別に納付する必要があります。
これは、相続人ごとに納める税額が異なるためです。
また、相続税の納税通知書は税務署から送られてきません。したがって、相続人自身が期限内に適切な額を納める責任があります。
これらのポイントを押さえ、適切な納税方法を選択して相続税を納付することが大切です。
申告・納付期限に遅れた場合
相続税の申告や納付期限に遅れてしまうと、いくつかのペナルティが課されることがあります。
①無申告加算税
無申告加算税は、相続税の申告期限を過ぎてから申告を行った場合に課される税金です。通常、納付すべき税額の10%が加算されますが、特定の場合には15%~20%に引き上げられることもあります。
無申告加算税は、期限内に申告を行うことで避けることができるため、早めの手続きが重要です。
②過少申告加算税
過少申告加算税とは、本来申告すべき財産額よりも少ない金額で申告し税金を納めた場合に、本来納めるべきであった税額との差額に対して課される税金です。
過少申告加算税は、本来納めるべきであった税額との差額に対して5%から15%が課されます。
③延滞税
延滞税は、相続税の納付期限を過ぎた場合に発生する税金です。納付が遅れるごとに、日数に応じて加算されるため、遅延が長引くほど延滞税の負担が増します。延滞税は、年利14.6%(日割り計算)で計算されるため、迅速な納税が求められます。
④重加算税
重加算税は、故意に過少申告や無申告を行った場合に課される厳しいペナルティです。重加算税は、納付すべき税額の35%から40%が加算されます。この税金は、意図的な脱税行為に対する制裁として課されるため、正確かつ誠実な申告が求められます。
これらのペナルティを避けるためにも、相続税の申告および納付期限を守ることが非常に重要です。
申告・納付期限に間に合わない場合
相続税は申告期限が過ぎてしまった場合でも、「期限後申告書」を提出することで、期限後の申告が可能です。
この場合、1日でも早く自主的に申告することが非常に重要です。早めに申告することで、無申告加算税や延滞税などのペナルティが結果的に軽減される可能性があります。
延長の申告ができる場合
場合によっては、相続税の申告期限を延長することが認められるケースもあります。
例えば、相続財産が海外にある場合や、その他の特別な事情がある場合です。この場合、申告期限前に税務署に対して延長の申請を行う必要があります。
今から準備しておけること

相続が発生した際、配偶者や子供などの法定相続人に迷惑をかけたくないと考える方は多いです。
相続手続きをスムーズに進めるためには、今から対策をしておくことが非常に重要です。
以下に、その具体的な対策を紹介します。
財産目録の作成
相続手続きで最も時間がかかるのは、相続財産の把握です。事前に財産目録を作成しておくことで、この手続きを大幅に簡略化できます。
私が父の相続手続きを行った際にも、必要書類の取得は思ったより時間がかかりませんでしたが、財産の把握には多くの時間を費やしました。
父の場合は、不動産と現金のみでしたが、借金などの負債も含め、すべての財産を記録しておくと、相続時、家族の心配が減り、安心して手続きを進められます。
遺言書の作成
財産目録とともに、遺言書を作成しておくことも重要です。遺言書により、自分の意思を明確に示すことで、家族間の争いを防ぐことができます。遺言書には、財産の分配方法や特定の相続人に対するメッセージを含めることができ、これにより相続手続きを円滑に進めることができます。
家族との話し合い
生前に家族と相続について話し合いを持つことも大切です。相続に対して問題意識がある場合、家族全員が理解し納得するために事前に話し合いを行うことが推奨されます。これにより、相続が発生した際にスムーズに対応でき、家族間のトラブルを防ぐことができます。
専門家への相談
相続に関する準備を進める上で、税理士や弁護士、相続コンサルタントなどの専門家に相談することも有効です。専門家は、法律や税務に関する詳細な知識を持っており、個々の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。
相続手続きをスムーズに進めるためには、今から対策を講じておくことが重要です。財産目録の作成や遺言書の準備、家族との話し合いを通じて、相続に関する不安を解消し、家族に迷惑をかけないようにしましょう。
専門家のアドバイスを受けながら、しっかりと準備を進めておくことで、安心して相続を迎えることができます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事では、相続税の申告と納付期限に関する詳しい情報と、今からできる対策を紹介しました。
相続税の申告や納付をスムーズに進めるためには、期限を守ることが非常に重要です。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生するため、早めの対応が求められます。
事前に財産目録を作成し、遺言書を準備しておくことで、相続手続きは大幅に簡略化され、家族間の争いも防ぐこともできます。また、専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けながら進めることもできます。
この記事を、身近な人への相続手続きやご自分の相続対策のヒントとしてお役立てください。家族全員が安心して過ごせるよう、しっかりと準備を進めていきましょう。