
どの種類を選べばいいのか分からない…
書き方を間違えると無効になるって本当?
もめない相続にするためには遺言書はとても重要です。
しかし、実際に準備しようとすると不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
本記事では、遺言書の3つの種類と、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。 また、遺言書の注意点も紹介します。
相続は適切な準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができ、大切な家族をしっかりとサポートすることができます。
この記事を身近な人への相続手続きのヒントにして下さい。
遺言書とは?
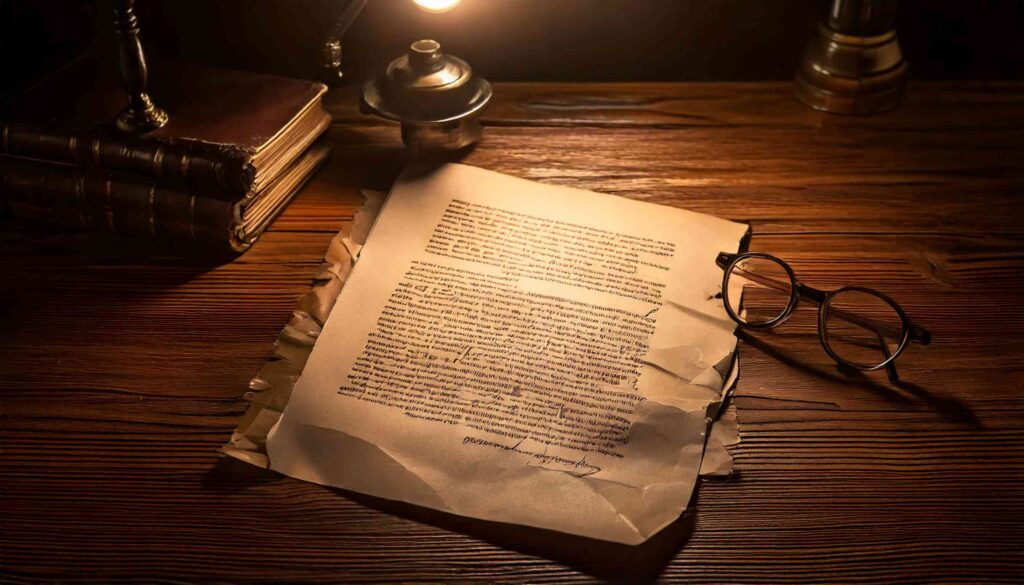
遺言書とは、財産の分配や家族へのメッセージなどを生前に書き残し、死後に自身の意思を実現するための重要な手段です。遺言書があることで、相続におけるトラブルを回避し、円滑な財産の引き継ぎが可能になります。
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの特徴や注意点を解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言書のことです。特別な手続きなしで作成できるため、最も手軽な方法といえます。
メリット
- 費用がかからない(紙とペンがあれば作成可能)
- 自分の好きなタイミングで作成できる
- 誰にも知られずに遺言を残せる
デメリット
- 内容に不備があると無効になる可能性がある
- 相続発生後に「検認」が必要
- 紛失・改ざん・隠匿のリスクがある
注意点
- 全文を自筆で記載する(代筆やパソコンでの作成は無効)
- 日付と署名を明記する(「〇月吉日」はNG、必ず「令和〇年〇月〇日」と記載)
- 押印する(実印が望ましいが、認印でも可)
- 財産の分配を明確に書く(「〇〇にすべてを相続させる」など、曖昧な表現は避ける)
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言のリスクを軽減するため、2020年7月から「法務局の保管制度」が導入されました。
【制度のポイント】
- 法務局で遺言書を保管できる(紛失・改ざんの防止)
- 家庭裁判所の「検認」が不要になる
- 相続人が検索できるため、遺言書の存在が確実に伝わる
- 保管申請時には遺言者本人が法務局に出向く必要がある
手軽さと法的確実性を兼ね備えた方法として、自筆証書遺言を作成する際には積極的に活用したい制度です。
参考:法務省ホームページ「自筆証書遺言書保管制度」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(2025年2月14日)
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。法的に確実性が高く、無効になるリスクが低いのが特徴です。
メリット
- 公証人が作成するため、法的に無効になる可能性がほぼない
- 家庭裁判所の「検認」が不要
- 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
デメリット
- 作成に費用がかかる(財産額に応じた公証手数料が必要)
- 証人2名が必要
- 公証役場で手続きを行うため、手間がかかる
注意点
- 公証役場に行き、公証人と相談する
- 証人2名を準備する
- 遺言の内容を公証人が作成し、本人・証人が署名押印
- 原本は公証役場で保管される。
公正証書遺言は、確実性が高く、相続トラブルを防ぎたい人におすすめです。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場で手続きを行い、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう遺言書です。
メリット
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる
- 公証人が関与するため、一定の信頼性がある
- パソコンで作成可能(自筆でなくても可)
デメリット
- 遺言内容のチェックはされないため、法的に無効となるリスクがある
- 相続発生後に家庭裁判所で「検認」が必要
- 紛失や改ざんのリスクがある
注意点
- 公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもと、遺言の存在を証明
- 封筒に公証人・証人とともに署名押印し、証明書を作成
秘密証書遺言は、「内容を知られたくないが、公的な証明を受けたい」という人に向いています。
まとめ
いかがだったでしょうか?
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
費用をかけず手軽に作りたいなら「自筆証書遺言」、法的に確実で、相続トラブルを防ぎたいなら「公正証書遺言」、内容を秘密にしつつ、公的な証明を受けたいなら「秘密証書遺言」になります。
また、自筆証書遺言を作成する場合は、法務局の保管制度を活用することでリスクを減らせます。
適切な準備をすることで、相続税負担を最小限に抑え、大切な家族を守るための相続手続きを実現できます。
相続対策を考えている方は、ぜひこの記事をヒントに、安心して準備を進めてみてください。
また、下記の記事も参考にして頂ければ幸いです。
遺言書ってどこまで自由に書けるの?そもそも何を書けばいいのか分からない…と感じている方も多いのではないでしょうか。こちらの記事では、遺言書で実現できることとできないことを詳しく解説しました。

※この記事は2025年2月15日時点の情報に基づいています。相続に関する法律は改正されることがあります。法律変更によって相続のルールに影響が出ることもあるため、最新の情報を踏まえて適切に対応してください。当社は税理士や司法書士ではありません。そのため、相続税の申告や登記手続きなど、税務や法律に関わる専門的な手続きについては、税理士や司法書士と連携しながら最新の法律をもとに対応しています。