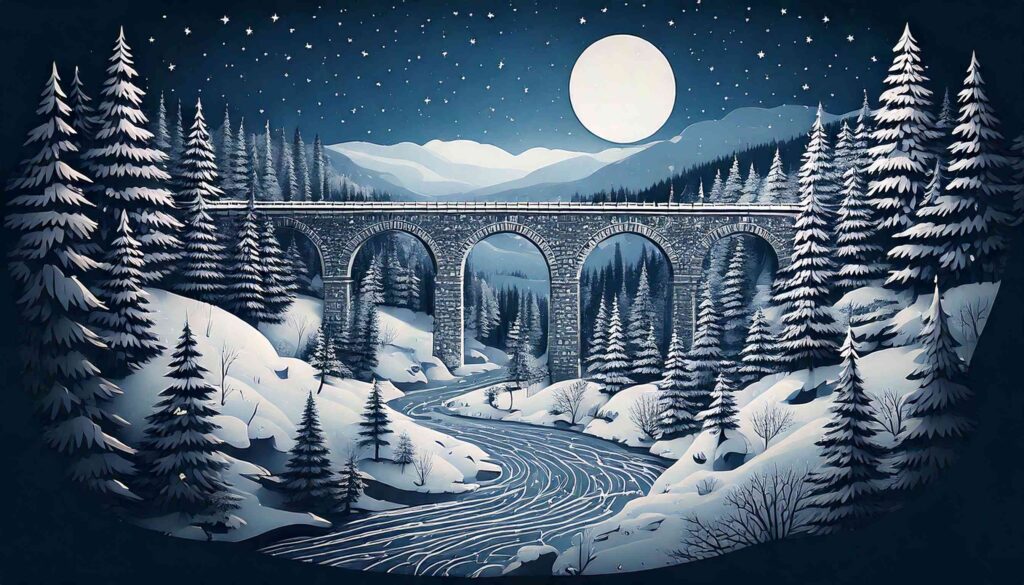
家族に障害のある方がいる場合、相続税の「障害者控除」を使うことでご心配を軽減できることをご存知でしょうか?
しかし、控除の適用を受けるには特定の条件や準備が必要です。
この記事では、相続税の障害者控除について、その概要や計算方法、必要書類、注意点を解説します。
大切なご家族を守り、円滑な相続をサポートするために、ぜひ最後までご覧ください。
相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除は相続人に障害を持つ方がいる場合に適用される控除制度で、相続税負担の軽減を目的としています。
この控除を活用することで障害者の生活を支えやすくし相続税の負担を減らすことができます。
適用には要件があり、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
要件
障害者控除を利用するためには次の要件が前提です。
- 日本国内に住所がある
- 85歳未満の障害者
- 相続や遺贈で財産を取得する法定相続人
また、上記の85歳未満の障害者とは、下記のような一般障害者・特別障害者を対象となります。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、遺産を受け取る権利を持つ人々のことを指します。こちらの「法定相続人とは?身近な人の相続手続きを支えるための基礎知識」では、法定相続人の基本的な内容と受遺者との違いや範囲と順位、相続権がない場合や放棄について詳しく説明しました。ご参考にして下さい。

一般障害者
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害等級が二級または三級である人として記載されている人
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が三級から六級までである人として記載されている人 など
特別障害者
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人で、重度の知的障害者と判定された人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級である人として記載されている人
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級である人として記載されている人 など
参照:国税庁HP「障害者の税額控除の対象となる人の範囲」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167_qa.htm(20241106)
計算方法
障害者控除の額は、一般障害者の場合、相続人が満85歳になるまでの年数に基づいて計算され、1年につき10万円が控除されます(1年未満の期間がある場合は切り上げて1年として計算)。
一方、特別障害者の場合は1年あたり20万円が適用され、85歳までの年数で計算されます。次に、具体的な計算式をご紹介します。
計算式
障害者控除の計算式は以下の通りです。
控除額 = 10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)
※特別障害者の場合は20万円
計算例
A:相続税100万円(Bの扶養義務者)
B:相続税100万円(一般障害者)
たとえば、50歳の一般障害者が法定相続人である場合、控除額は以下のように計算されます。
10万円 × (85歳 − 50歳) = 10万円 × 35年 = 350万円
この場合、相続税から350万円が控除されるのでBの相続税は0円になります。
そして、Bの引ききれなかった控除額を扶養義務者であるAの相続税から引くことができます。
相続税100万円 ‐ 250万円 = 0円
※扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
障害者控除の必要書類
- 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
- 障害者手帳のコピー
参照:国税庁HP「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r06pdf/C20.pdf(20241106)
注意点
障害者控除を適用する際には、以下の点に注意が必要です。
まず、過去の相続で同じ障害者に対して障害者控除が適用されている場合、今回の相続で適用できる控除額が制限される可能性があります。2回目の適用となる場合は、初回とは異なる計算式が用いられ、控除額が調整されるため、前回の控除内容を確認することが重要です。
また、障害者控除を適用した結果、相続税が0円になる場合は、相続税の申告自体が不要になります。この点を知っておくことで、不要な手続きを避けることが可能です。
さらに、障害者控除を受けるためには制度の適用要件を満たし、必要書類を整えることが求められます。特に、障害者手帳の提出が必須となるため、申請を検討する際は早めに手帳の取得を進めることが推奨されます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事では、相続税の障害者控除について、概要から計算方法、必要書類、注意点までを詳しく解説しました。障害者控除は、障害のあるご家族の経済的な支えを目的とした制度で、適用条件を満たすことで相続税負担を大幅に軽減することができます。これにより、相続後も障害を持つ家族が安定した生活を送りやすくなります。
控除を受けるためには、要件を確認し、必要な書類を早めに準備することが大切です。
また、申告や手続きが複数回にわたる場合もあるため、専門家のサポートを受けながら計算や申告を進めると安心です。
事前にしっかりとした準備を整えることで、相続手続きをスムーズに進め、大切なご家族の未来を支える助けとなります。