
遺言書ってどこまで自由に書けるの?そもそも何を書けばいいのか分からない…と感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、初めて相続を考える方にとっては、遺言書にどこまでの効果が期待できるのかがわかりにくいものです。
実は、遺言書に記載できることには限りがあり、その内容によっては法的に実現できない場合もあるのです。
本記事では、遺言書で実現できることとできないことを詳しく解説します。
遺言書ってどこまで自由に書けるの?そもそも何を書けばいいのか分からない…と感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、初めて相続を考える方にとっては、遺言書の作成にどこまでの効果が期待できるのかがわかりにくいものです。
実は、遺言書に記載できることには限りがあり、その内容によっては法的に実現できない場合もあるのです。
本記事では、遺言書で実現できることとできないことを詳しく解説します。
遺言書さえ作れば…
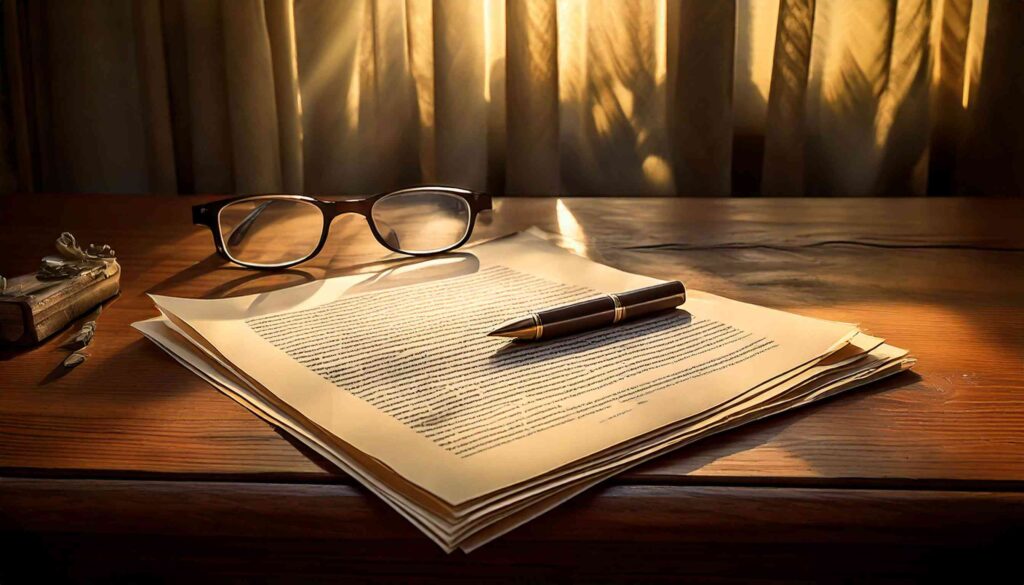
遺言書は、自分の財産や家族に関する意思を法的に残すための大切なツールです。しかし、「遺言書さえ作ればすべての希望が叶う」と思っていませんか?
実は、遺言書に記載できることには法律上の制限があり、その内容によっては実現できない場合もあります。
例えば、遺言書で財産の分配や特定の人への遺贈は可能ですが、相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害することはできません。また、事業継承の希望や家族への感謝の気持ちを記載しても、それらには法的効力がないこともあります。
以下から「できること」と「できないこと」を順番に説明していきます。
遺言書でできること
遺言書は法的に有効な意思表示として、財産の分配や家族に関するさまざまな故人の思いをサポートします。以下に具体例を挙げます。
財産の分配・処分
遺言書は、遺産の分配や処分に関して、法定相続分を超えた自由な意思を反映できる貴重な手段です。遺言書を活用することで、特定の相続人に多くの遺産を取得させたり、分割方法を指定したりすることが可能です。
また、相続人でない人や団体に財産を遺贈することもできます。
身分について
家族や身分に関する意思を示すこともできます。特に「子どもの認知」や「相続人の廃除」といった重要な決定についても、遺言書を通じて法的な効果を持たせることが可能です。
遺言の執行
遺言書は、財産の分配だけでなく、遺言者の意思を確実に実行するための「遺言の執行」に関する内容も記載できます。
特に、未成年の子どもや、判断能力が十分でない家族がいる場合の後見人の指定や遺言書の内容を実際に執行する責任者として、遺言執行者の指定することは、遺言の内容を確実に実現し、家族が安心して手続きを進めるために重要な役割を果たします。
遺言書でできないこと
遺言書は、遺産分配や家族に関する意思を法的に示すための非常に重要な手段です。しかし、遺言書に記載した内容すべてが法的効力を持つわけではありません。ここでは、遺言書でできないことについて詳しく解説します。
「遺留分」を侵害することはできない
遺言書で財産を自由に分配できるとはいえ、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保証されています。
遺留分を侵害する遺言内容は無効となる可能性があり、相続人から遺留分減殺請求を受けることもあります。
例えば、「すべての財産を特定の人に渡す」という遺言があったとしても、遺留分を持つ相続人がいる場合にはその取り分が保障されるため、意図した内容が実現できない場合があります。
子の認知以外の身分に関する事項
遺言書では「子の認知」を行うことはできますが、その他の身分に関する決定(養子縁組・離縁・結婚・離婚など)はできません。
家族への願い・感謝の気持ち
遺言書に家族への願いや感謝の言葉を記載することは自由ですが、これらは法的な効力を持ちません。
たとえば、「子どもたちが協力して事業を続けてほしい」という希望や、「配偶者に感謝している」という思いを遺言書に記しても、それはあくまで遺言者の気持ちを伝えるものであり、法的拘束力はありません。
ただし、家族に向けた手紙として活用することで、心情を伝える大切な役割を果たすことができます。
その他
遺言書で事業継承に関する意思を示すことはできますが、法的拘束力はありません。事業の継承は、株式や資産の分配といった具体的な内容を伴うため、遺言書だけで解決するのは難しい場合があるからです。
また、遺言書は満15歳以上の人で意思能力があることが条件です。意思能力がない場合、遺言書は無効とされるため、遺言者の状態が適切な時期に準備することが重要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
この記事では、遺言書の効力について、「遺言書でできること」と「遺言書でできないこと」を解説しました。遺言書には、財産の分配や身分に関する意思を記載できる一方で、記載内容によっては法的に実現できない場合もあります。そのため、遺言書を正しく理解し、活用することが大切です。
遺言書は、大切な家族を守るための重要なツールです。しかし、内容に不備があったり、法的効力を超えた希望を記載してしまうと、家族間のトラブルや相続手続きの遅延を招く可能性があります。これを防ぐためには、遺言書の限界を理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
適切な準備をすることで、相続税負担を最小限に抑え、大切な家族を守るための相続手続きを実現できます。
相続対策を考えている方は、ぜひこの記事をヒントに、安心して準備を進めてみてください。
※記事は2025年1月29日時点の情報に基づいています。相続に関する法律は改正されることがあります。法律変更によって相続のルールに影響が出ることもあるため、最新の情報を踏まえて適切に対応してください。当社は税理士や司法書士ではありません。そのため、相続税の申告や登記手続きなど、税務や法律に関わる専門的な手続きについては、税理士や司法書士と連携しながら最新の法律をもとに対応しています。